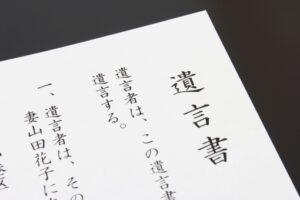「ゆりかごから墓場まで」— 人生の各ステージのファイナンシャル・プランニング【連載32】
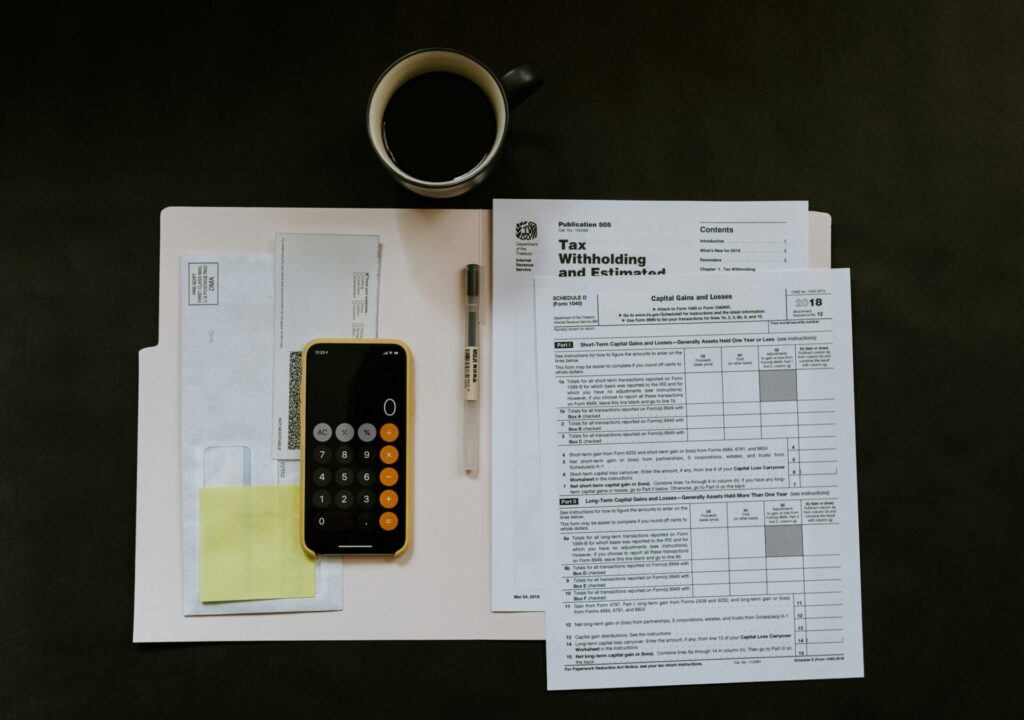
相続税の基礎知識と節税対策
目次
相続はすべての家庭に起こりうる重要なライフイベントです。
特に近年では、都市部の不動産価格の上昇や高齢者の資産増加により、「相続税は一部の富裕層の問題」という時代は終わりつつあります。
本項では、相続税の基本的な仕組みと、節税のために事前にできる対策について解説します。
◆ 相続税とは?どんなときに課税されるのか
相続税は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続や遺贈によって受け取ったときにかかる税金です。
課税されるかどうかは、相続財産の合計額と、法定相続人の人数によって決まります。
◆ 相続税の基礎控除の計算方法
まず、相続税が課税されるかどうかを判断するには、以下の「基礎控除額」で判断します。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
▸ 例:相続人が配偶者と子ども2人(計3人)の場合
→ 基礎控除は 3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円
この金額を超える相続財産がある場合、相続税の申告・納税が必要となります。
◆ 課税対象となる財産の範囲
相続税の対象となる財産には、次のようなものが含まれます:
- 預貯金・株式・投資信託
- 土地・建物(自宅含む)
- 家財・骨董品・車など
- 生命保険金(一定額は非課税)
- 死亡退職金(一定額は非課税)
- 相続開始前3年以内の贈与(課税対象)
※負債(借金)や葬式費用などは差し引くことができます。
◆ 相続税の節税対策(生前にできる主な方法)
相続税は、事前の準備次第で大きく軽減することが可能です。以下に代表的な対策を紹介します。
▸ ① 生前贈与の活用
- 暦年贈与:1人あたり年110万円までは非課税(毎年コツコツ贈与する)
- 相続時精算課税制度:2,500万円まで贈与時非課税(ただし相続時に加算)
※令和6年(2024年)からは、贈与加算期間が3年→7年に延長されるなど制度改正あり。
▸ ② 生命保険の非課税枠を活用
- 相続人が受け取る生命保険金は、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税
▶ 例:相続人3人 → 1,500万円までは相続税がかからない
▸ ③ 不動産の評価差を利用する
- 不動産は「路線価(時価より低い評価額)」で計算されるため、現金よりも相続税を抑えられる傾向にあります
- 賃貸物件にすると評価がさらに下がる(貸家建付地評価)
▸ ④ 家族信託の活用(認知症対策+相続管理)
- 認知症による資産凍結を防ぎ、円滑な資産承継が可能
- 不動産の売却・賃貸なども信託された家族が管理できる
◆ 相続税の申告・納税の流れ
- 相続開始から10ヶ月以内に申告・納税が必要
- 原則、現金一括納付(延納や物納も条件付きで可能)
- 相続税の申告書は税理士に依頼するのが一般的
◆ まとめ:「知らなかった」では済まされない相続の税金
相続税は、「資産の多い少ない」よりも「準備していたかどうか」で負担が大きく変わる税金です。
いざという時に慌てないためにも、財産の把握、相続人との話し合い、制度の理解を今から進めておくことが、結果的に家族の安心と節税につながります。